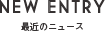2015.06.28
エゾマツ

名称・・・蝦夷松(Yezo spruce、Hokkaido spruce)
その他呼び名・・・
黒蝦夷松(クロエゾマツ)、黒松(クロマツ)(北海道での呼び名)(*1)
科目・・・マツ科トウヒ(Picea)属・常緑針葉樹・裸子植物
学名・・・Picea jezoensis Carriere
産地・・・北海道、本州の中部山岳地帯、紀伊半島の大峰山(おおみねさん)。千島、サハリン、樺太、中国北東部、朝鮮にも分布。
色調・・・心材、辺材共淡い黄白色。
性質・・・木理:通直、辺心材の境目:不明瞭、肌目:緻密、硬さ:やや軟~中庸、腐食耐久性(耐朽性):極めて弱~弱、磨耗耐久性:弱
気乾比重:0.35~0.43(平均値)~0.52
平均収縮率%(柾目方向):0.15
平均収縮率%(板目方向):0.29
曲げ強度MPa:69
圧縮強度MPa:34
せん断強度MPa:6.9
曲げヤング係数GPa:8.8
加工性・・・鋸挽(ノコビキ):容易、鉋掛(カンナガケ):良好~やや困難(樹脂による障害)、釘打保持力:やや弱、糊付接着性:良好、乾燥:容易、塗装性:注意
用途・・・構造材、下地材、造作材、建具、家具
土木材、パルプ材、楽器材(ピアノ響板、ヴァイオリンの甲板)、船舶材、土木材、木毛、経木。
価格・・・☆
メーカー・・・
一般流通サイズ・・・サンギ:48x24x3650(\65,000/㎥)
その他・・・
北海道ではトドマツと一緒にしてエゾトドと呼ばれる。北海道で主として用いられ、本州で柱や板に使っている杉のようにエゾ・トドが使われている。造作材としては北海道、北陸地方以外での使用は少ない。類似種にアカエゾマツやトウヒ(*2)、ハリモミ、イラモミがあり、何れも酷似している。
【その他色調等】: 表面仕上げ良好。美しい光沢を持つが樹脂成分が多い。斑の模様不明瞭。年輪はやや明瞭で、年輪の幅は比較的均一。長期間大気に触れているとかなり色が濃くなる。小さな死節やヤニツボが現れることがある。心辺材の中間にあたる部分に淡紅~赤褐色が現れることがあるが、褐色みの強いものは腐朽の前提である。
【その他性質等】: 割れやすい。比重の割りに強い良材。ほとんど臭いがない。軸方向細胞間道(樹脂道)をもっているが、材面にヤニが滲み出てくることはあまりない。収縮が小さい。
【立木での性質等】:樹高30m以上、樹径1.0m~1.5m。樹皮は黒くて硬い鱗状。
*1:一般にクロマツというと日本産でマツ科マツ属の別種類があります。紛らわしいですね。
*2:日本産のトウヒはエゾマツの変種で、学名はPicea jezoensis var.hondoensis です。