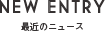2015.06.25
カリン

名称・・・花梨(花欄・花林)(Chinese quince)
その他呼び名・・・
印度紫檀(インドシタン)(印度花梨(インドカリン))、ヤエヤマシタン、ナーラ(ナラ)(フィリピンでの呼び名)、リングア(リンクワ)、アンサナ(アングサナ)(インドネシアでの呼び名)、パドウク(パドック)(ミャンマーでの呼び名)、ニューギニアローズウッド(パプアニューギニアでの呼び名)、セナ(マレーシアでの呼び名)、本花梨(ホンカリン)、ビルマカリン(ビルマシタン)、プラドウ
科目・・・マメ科ソラマメ亜科シタン(Pterocarpus)属・広葉樹・環孔性散孔材・離弁花類(被子植物)
学名・・・
Pterocarpus indicus Willd
Pterocarpus macrocarpus(ビルマカリン)
産地・・・タイ、ミャンマーなどの東南アジアに多く、フィリピンを経てニューギニアなど
性質・・・木理:かなり交錯、辺心材の境目:明瞭、肌目:やや粗、硬さ:極硬、腐食耐久性(耐朽性):強、磨耗耐久性:強
気乾比重:0.52~0.74
平均収縮率%(柾目方向):0.12
平均収縮率%(板目方向):0.20
曲げ強度MPa:70~98
圧縮強度MPa:51~54
せん断強度MPa:10.5~11.4
曲げヤング係数GPa:10.4~12.1
加工性・・・鋸挽:やや容易~(困難)、鉋掛:やや容易~(困難)、釘打保持力:強、糊付接着性:良好~中、乾燥:中~困難、塗装性:注意
用途・・・造作材、家具
器具、楽器、装飾材、床柱、床廻り材、スライスドベニヤ、唐木細工、指物、三味線の胴、重構造材、車輌材、羽目板、床張
価格・・・☆☆☆☆☆~
無節材(2000x210x34㎜)150万/㎥
メーカー・・・
一般流通サイズ・・・
その他・・・
唐木のひとつ。一般に均一な色調を示すことは少なく、縞模様になることが多い。表面仕上は良好。ただ仕上げ時に逆目が立ちやすい。ゆっくりと乾かさないと乾燥によって狂いやすい。磨くと光沢が出て美しい。バラ科の果樹・花木として知られるカリンとは全く別の種類。日本産ナシ科のカリンも榠櫨や花輪と書き全く別の樹種。同属の樹種にアフリカ産のアフリカンパドウク(学名:Pterocarpus soyauxii)がある。同属の類似の種類があり、ローズウッドなどはカリンとして扱われることがある。広義にはシタン類の一種で、中国名では紫檀とされる。斑の模様不明瞭。インドシナに生育し大木になる。通常の樹高は10m、樹径0.8m程度だが樹高30~45m、樹径1.8mにも達する。材の浸漬液(木材を削り試験管に入れて水を注いだもの)を太陽光にかざすと美しい蛍光を発する。シタンやコクタンの代替材として用いられることが多い。シタンよりやや軽軟で材質は劣る。
備考・・・
インドシタン=ナーラ=リングア(フィリピン、インドネシア産)が学名:indicusの樹種で、ホンカリン=ビルマカリン=パドウク=プラドウ(タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム産)が学名:macrocarpusの樹種として二つを分けようとしていることもあります。
同属の樹種にアフリカ産のムニンガ(学名:Pterocarpus angolensis)というのもあるみたいです。