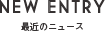2015.06.22
ミズメ

名称・・・水目(Japanese cherry birch)
その他呼び名・・・
水目桜(ミズメザクラ)、夜糞峰榛(ヨグソミネバリ)、梓(アズサ)、アズサカンバ、サクラ、コッパダミネバリ
科目・・・カバノキ科カバノキ(Betula)属・落葉広葉樹・散孔材・被子植物
学名・・・Betula grossa
産地・・・本州、四国、九州の深山に生える。
色調・・・心材は紅褐色。辺材は黄色を帯びた白色。黄白色。心材の色はマカンバに比較すると赤身が濃いといえる。
性質・・・木理:通直、辺心材の境目:明瞭、肌目:緻密~やや緻密、硬さ:硬、腐食耐久性(耐朽性):弱~中、磨耗耐久性:{弱/中/強
気乾比重:0.60~0.72~0.84
平均収縮率%(柾目方向):0.18
平均収縮率%(板目方向):0.32
曲げ強度MPa:108
圧縮強度MPa:49
せん断強度MPa:14.7
曲げヤング係数GPa:13.7
加工性・・・鋸挽(ノコビキ):容易~中、鉋掛(カンナガケ):中、釘打保持力:{弱/強、糊付接着性:中、乾燥:中、塗装性:中
用途・・・造作材、家具
器具材、床材、機械材、床柱、洋風の内装用材、漆器木地、版木、柄
価格・・・☆☆☆
メーカー・・・
一般流通サイズ・・・平割:34㎜、60㎜
その他・・・
日本特産の材。蓄積量はあまり多くない。カンバのなかでは南方系で、関西より西でも目にすることがある。あまり大径木にはならない。樹高20m。年輪はやや不明瞭。表面仕上げは良好。割裂性は小さい。マカンバの特徴と同じく、製品になった時の安定性、材質の均一性などを持っている。木材の保存性は低く、辺材はヒラタキクイムシの害を受けることがある。材が硬くて弾力がある為、古くは梓弓(あずさゆみ)といってミズメで弓を作った。ミズメの名前は、枝でも幹でも傷をつけると水のように樹液をだすことからつけられた。この樹液には香りがあり、香気成分はサロメチール(サルチル酸メチルエステル)で、枝葉にもサロメチールのにおいがあるため、ヨグソミネバリとも呼ばれる。また、カンバの類は取引上よくサクラと呼ばれることがあり、ミズメも若い樹皮や材の外観がサクラに似ていることから、銘木界ではミズメザクラと称される。勿論サクラの類とは関係がない。家具や内装材にはミズメがサクラの名前で使われることが多く、現在では真正のサクラはほとんどないと思われる。
備考・・・
シロザクラやキングウッドと呼ぶという資料がありましたが、その一つしか確認できませんでした。真偽は不明です。ちなみにシロザクラと言うと色々あるようで、イヌザクラやミヤマザクラもシロザクラと言うようです。ただ建築用材でシロザクラというと、シラカバを指すことが多いでしょう。